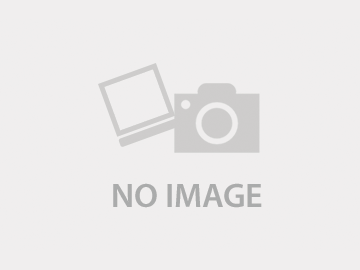今回は「脱力の大事 スポーツ編」として、身体を動かす際にも脱力がとても大事であることをお伝えしたいと思います。
これは、スポーツに限らず、普段の生活の中で無意識に身体を動かしている時にも必要な内容となりますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。
●握る力は適切ですか?
何かを握るスポーツと言えば道具を使うスポーツですから、ゴルフ、テニス、野球、陸上でも道具を使う競技はあります。
多くのスポーツが道具を使用してプレイすることを考えると、この道具をどう扱うかがスポーツを上達させる第一歩になることは間違いありません。
その第一歩の前に重要になることが、道具を握る力加減になります。
運動をしているのだから力一杯振ったり、投げたりするのが当たり前だと思われる方も少なくないと思います。
ただ、その力一杯の中に道具を握る力も一杯になってしまうと、しなやかな動きも、素早い動きもできなくなってしまうのです。
自動車や、自転車の運転をされる方であれば理解し易いと思いますが、ハンドルをガチガチに強く握っている状態では、素早くハンドルを切ろうと思っても反応が遅くなり素早くハンドルが切れなくなります。
その他の日常生活の中で例を挙げると、包丁で食材を切る際にも握る力が強くなることで、しなやなで素早い包丁捌きができなくなってしまいます。
●力を入れて運動すると壊れます
しなやかな動きができなくなるということは、力が入り過ぎていることにより関節の可動域が減少している状態にあります。
その可動域の減少を補うためには、筋肉の力を使って可動させようとしますから、必要以上に筋肉に負担を掛けることになります。
筋肉は、簡単に言えばゴムのような動きをするものです。
伸び縮みをするのが仕事ですから、力を入れていては縮むことしかできていません。
伸びが無ければ良い縮みも得られませんので、効率の良い筋肉の仕事ができなくなってしまうのです。
スポーツをしている時に、力技(筋肉の収縮の強さ)だけでプレイされる方は、身体の能力を最大限に効率良く発揮できないだけでなく、いずれ身体が壊れる可能性が高くなってしまいます。
これは、無理な体勢で物を持つことや、椅子から立ち上がるようなことなどにも共通して言えることとなりますので、一度日常生活の中でも意識していただきたいと思います。
●イチローの身体は壊れない!
イチローさんに対するイメージを挙げるとすると、
「怪我で休むことが無い」
これがひとつは挙がると思います。
イチローさんの身体が壊れない秘訣が脱力にあると僕は思っています。
イチローさんの筋肉は、赤ちゃんのようにプニプニの筋肉で、肩甲骨と横隔膜の隙間には余裕で指が入るくらい柔らかい状態になっています。
重いバットを振り込んでいても、腕の筋肉がプニプニなのには驚きました。
このプニプニの筋肉を作っているのが脱力なのです。
イチローさんのバッティング時の映像や画像を観ると、ほっぺたを膨らませて振っているものが多くあります。
実際に、イチローさんのバッティング練習を真後ろで観察した時に一番印象に残ったことが、息を「フーッ」と吐きながら振っていることでした。
「フーッ」という声が聞こえるくらいの息の吐き方なので、歯を強く食いしばることをしていないことが分かります。
この癖に共通する選手が大谷選手です。
大谷選手も打つ時、投げる時両方でほっぺたを膨らませてプレイしています。
プロテニスプレイヤーもそうですが、声を発しながらボールを打っています。
この逆に、明らかに力を入れてプレイしていた選手で印象的だった方が清原さんです。
西武ライオンズに在籍していた頃は柔らかいスイングでしたが、ジャイアンツに移籍してからは力づくのスイングに変化して行きました。
ジャイアンツに移籍してからのトレーニングをテレビで観ると、歯を食いしばりながら大きな筋肉を作るウエイトトレーニングをされていた映像を多く観ることがありました。
バッターボックスに入って、構えている時からガチガチに力が入っているように観え、顔を赤くするほど力んでスイングしているように見えました。
実際の清原さんの言葉で、「バッティングの時に強く歯を食いしばって打つので奥歯がボロボロになります。」
といったコメントをされていたことが強く記憶に残っています。
清原さんの現役時代を振り返ると、ジャイアンツ以降は怪我が多い野球人生となりました。
これらのことから、スポーツをする際の脱力が、成績の向上と怪我の防止になることが分かります。
これは、日常生活に於いても同様であり、動作する際の「よいしょ」「どっこいしょ」といった掛け声はとても大切なのだと思います。
またまた長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。
脱力については、健康を手に入れるための大事な要素のひとつとなりますので、できるだけ詳しく、分かりやすくご説明させていただきたいと思っております。
次回は、脱力のテーマの最後としまして「脱力の大事 実践編」をお伝えしたいと思います。
各務原活法整体センター
後藤周士